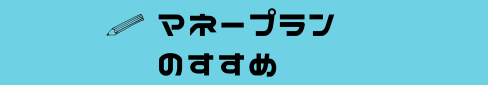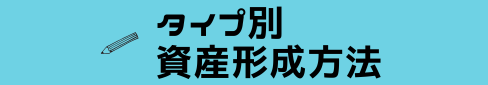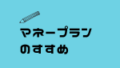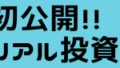[PR]本記事には広告が含まれます。
現代は終身雇用等で会社に頼ったマネープランは成り立たなくなっています。また、年金制度に頼ると、将来充分なお金が無く希望の暮らしが実現できない可能性も。
そんな背景の中、国は新NISA制度を開始するなど各個人による資産形成を後押ししています。希望の暮らし方を実現し、将来老後に備えるためにも、資産形成は今や避けては通れない物です。
「マネープラン作成手順」でライフプランとマネープランを作成した皆さんは、いつ頃どのくらいのお金が必要になるのか判るようになりました。ライフプランに合わせ、さっそくご自身に合った方法で資産形成とマネープランの改善を始めていきましょう。
本記事では、あなたの性格、現在の資産状況、資産形成にかけられる期間等からタイプ別におすすめの資産形成方法をご紹介したいと思います。
安定志向の人向け
リスクを取りたくない、お金が減ってしまうのは耐えられない!そんな方にお勧めの方法は貯蓄型の資産形成方法です。単なる貯蓄ではなく、お得な金利でゆっくりでも資産を増やせる方法はいくつかあります。
・積立定期預金:毎月一定額を自動で積み立てしていく預金方法が積立定期預金です。少額からコツコツ貯められて元本保証があるので安心です。
定期預金口座へお金を積み立てる事で自由に引き出しにくくなるので、お金を使ってしまって中々貯められない方や先取り貯蓄を行いたい方におすすめの方法です。自由に引き出せる普通預金よりも良い金利が設定されている事が多いです。
・財形貯蓄制度:会社員の方向けの方法です。会社が給与天引きで自動で指定の積立口座に指定額を入金してくれます。住宅・年金・一般の3タイプあり、目的に応じて用途を選択し、必要になった時に引き出せます。新社会人の方など、これから資産形成を始められる方や、まだ貯めクセのついていない方、住宅購入予定がある方などにおすすめの方法です。
・貯蓄型保険:保険と資産形成を兼ね備えた保険商品です。満期時にまとまった資金が受け取れるので、ライフイベントに応じた資産形成を目指したい方におすすめの方法です。保険会社によって色々な商品があるので、専門家に相談して選択しましょう。
・金利の高いインターネットバンキングに切り替える:金利の上昇に伴い、金利収入も以前と比較して貯蓄性のあるものになってきました。メジャー銀行よりインターネットバンキングの方が一般的に高い金利設定になっていますが、特におすすめしたいのがインターネットバンキングのSBI新生銀行です。メジャー銀行の金利支払いが年2回なのに対して、SBI新生銀行は2か月に1回=年6回の金利支払いを得られるので、ゆっくりでも着実に貯蓄を増やすことができます。
リスク許容型 増やしたい人向け
リスクを取っても積極的にお金を増やしたい人におすすめの方法は株式や投資信託などへの投資による資産形成方法です。
・新NISA(少額投資非課税制度):投資信託や株式を非課税で運用できる制度で2024年より始まりました。初心者にも人気で、新NISAの開始に伴い新規に株式市場に参加する一般消費者が増え株式市場は活発化しています。元本保証はなく、経済動向や株式価格の変化によって資産が増えたり減ったりするリスクがありますが、一般的に貯蓄型と比較して高い利回りを得ることができ、資産の増えるスピードは速いでしょう。
[PR]これからNISAを始めたい方におすすめの証券口座は松井証券です。
NISAでの株式取引手数料は無料な上、投資先の判断に役立つ銘柄情報や会社四季報など、情報が見やすいと評判です。また、資産運用を学びたい方に嬉しい無料動画や記事も提供しており、これから資産運用を始める方に役立つ機能が満載です。
・iDeCo(個人型確定拠出年金):老後資金を積み立てながら所得控除のメリットも得られる制度です。投資先は株式市場や投資信託、債券等で、上記新NISAと同様に元本保証はありません。またお金の引き出しは原則60歳からとなりますので、長期運用を行いたい人向けです。
・ロボアドバイザー:株式投資の手法の一つとして、AIが自動で資産運用してくれるサービスも増えています。投資先企業の決算資料など読み込むのは難しかったり、時間がないというケースもあります。AIが代わりに運用してくれるので、知識がなくても始めやすいと言われています。元本保証はなく、AIであっても経済や株式市場動向を完全には予測できませんので、リスクがある資産形成方法です。
長期運用型
一般的に、資産形成は早く始めるほど有利と言われています。それは長期に渡って運用することで複利効果が得られ資産が増えやすくなるからです。
その為、まだ年齢の低い20/30/40代の方は長期運用を前提に資産形成を進めると将来に必要なお金に沿った資産形成がしやすいと言えるでしょう。
長期運用型の方は、リスク許容型へ移行しハイリターンを狙いやすくなるでしょう。
なぜなら、ある一点で損失が出たとしても、そこで諦めるのではなく長期に運用を継続していくことで、複利効果による資産増加と市場成長による資産増加が期待できます。
あくまでも経済学的考え方に則ったものですので、必ずその通りになるとは限らないことは年頭に置いておく必要があります。
また、投資では複数の資産に分けて投資する分散投資によりリスクを抑える考え方がありますが、長期運用の場合は、投資先の分散だけでなく、投資時期の分散も可能です。経済が上昇基調と低迷基調が交互に起こりながら成長します。ある単年度にまとめて投資・運用するのではなく、複数年にまたがって投資することで、時期的に分散された投資を実現できます。
結婚・住宅購入・教育費・老後などのライフイベントに備えて、時間を味方につけることで、リスクを減らしながら資産を増やしていくことができるでしょう。
短期運用型
一口に短期運用と言っても、年齢の低い方が短期で資産を増やすのか、あるいは年齢の高い方で短期の運用期間しか確保できないのかによって、異なる資産形成方法になってきます。
若年層の短期運用型
短期運用といえば、デイトレードのようなその日のうちに売買を完了するような短期運用を思い浮かべるかもしれませんが、市場をこまめにチェックする必要があったり、損失リスクも高いので、長期的な人生設計を目指すライフプランの観点からは難しい点もあります。
一般的に働き始めたばかりの若年層の場合はまだ資産額が大きくないケースがありますので、まずは資産運用の元手作りを目指して短期での資産作りを始めてはいかがでしょうか。
先にご紹介した銀行の定期預金サービスで元手を少しずつ作っていく、新NISAのつみたて投資枠で非課税枠を活用しながら元手を作っていく等がリスクの低い運用方法です。
もう少しリスクを取るのであれば、以下のような方法もあります。
- 株式投資による配当収入や売却益を得て資産を増やす
- IPO投資で売却益を得て資産を増やす
- Paypay等のポイント投資でハイリスク・ハイリターン運用を目指す
短期で資産運用の元手ができたら、積み立ててきた投資額をそのまま長期運用していくとも可能ですし、更に運用額を増やして資産をどんどん増やしくいくこともできるでしょう。
シニア層の短期運用型
シニア層の短期運用と考えると、退職金の短期運用がまず頭に浮かぶかと思います。
退職金の短期運用では、「元本を守りつつ、少しずつ増やしていく」という考え方が主流になります。退職金は第二の人生の大切な資金です。慎重にバランスを取りながら運用していきましょう。
以下のような方法があります。
- 退職金専用の定期預金:金利優遇があり、元本保証で安心です。
- バランス型投資信託:短期運用のため投資期間分散によるリスク低減は難しいですが、複数資産に分散投資するバランス型の投資信託を選択することで、分散投資によるリスク低減が期待できます。
- ETF(上場投資信託):株式のように売買が可能なので、急にまとまったお金が必要になった時も売却して現金化できます。投資信託のように複数銘柄が含まれるので分散効果を得られます。
シニア層の資産運用は、損が出た時に取り返す時間が限られるため一般的にリスクが高くなります。そのため、半年~1年分の生活費は預金で確保したり、分散投資を徹底するなど、リスク低減の意識が大切になります。「増やす」ことに注力するあまり資産が減らないよう、「減らさない意識」をもって守りの運用をしていきましょう。
うまい話には罠があります。安全性と流動性を意識してくださいね。
おわりに
タイプ別におすすめの資産形成方法をご紹介しました。
資産運用はまだこれから、という方はまずは適切な銀行口座、証券口座の準備から始めましょう。
[PR]
NISAでの株式取引手数料が無料、NISA以外でも1日の約定代金合計50万円以下の株式取引手数料が無料などサービスが充実している松井証券での口座開設がおすすめです。
投資先の判断に役立つ銘柄情報や会社四季報など情報が見やすいと評判で、資産運用を学びたい方に嬉しい無料動画や記事も提供しており、これから資産運用を始める方に役立つ機能が満載です。
![]()
あなたにあった資産形成方法を選択して、無理なく資産形成とマネープランの実現・改善を進めていきましょう。
以上